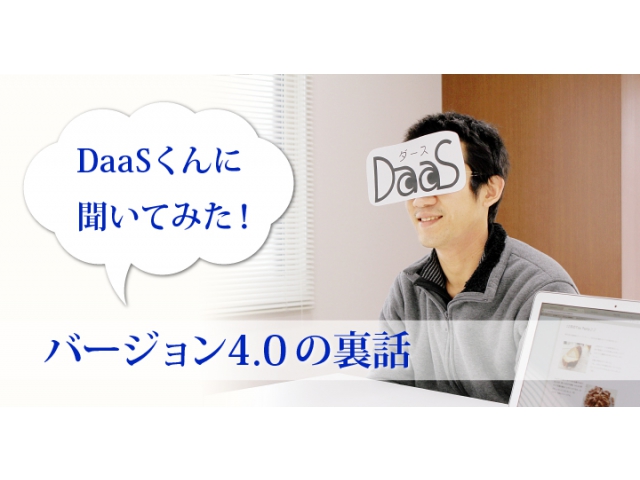2017/1/18
[vol.122]DaaSくんに聞いてみた! バージョン4.0の裏話
読んで【実】になる☆もぎたてマガジン『e-ラボレター』
デルターの仕事始めは、スタジオがある地域の氏神様へのご挨拶からスタートします。参拝後、社長が引いたおみくじは大吉!「する事なす事幸の種となって 心配事なく嬉しい運ですから わき目ふらず一心に自分の仕事大事とはげみなさい」とのこと。このご利益を、みなさまと分かち合える一年になりますように☆
デルターの取り組み特集
「DaaSくんに聞いてみた! バージョン4.0の裏話」
デルターのオリジナルCMS(ホームページ更新システム「DaaS(ダース)」は、2016年11月にバージョン4.0をリリースしました。一番の売りは、レスポンシブWEBデザインつまり「スマホ対応」になったこと。この大革命について、DaaSくんに突撃インタビューしました!
DaaSくん曰く、昨今の流れは「Simple is best」。以前の流行りで装飾過多だったサイトは、スマホやタブレットでは見づらくありませんか?装飾過多ということは余分が多いということで、目移りして本当に見たい情報にたどり着きにくいものです。つまるところ、情報がぼやけてしまいます。
そもそも何のためのCMSかと言うと、閲覧者がどのデバイスで見ても、見たい情報をスムーズに見られるため。そして、サイトを管理するCMS利用者の誰もが、ある程度直感的に操作でき、その結果伝えたいことがきちんと伝わることが大切です。
実は他社のCMSはもっと自由で、一文字ずつ色を変えられるものもあります。ですが、DaaSくんに言わせれば「彩るということは装飾の一種で、やり過ぎるとやっぱり情報がぼやける」とのこと。
DaaSでは、ある程度の制限を設けることで美しく見せています。それぞれのサイトにはテーマカラーがあり、それをベースに強調色やリンク色を決めて設定しています。
今回のバージョンアップでは、そこもシステム化しました。作業スピードを上げて、コストを下げたのです。これは、今まで以上に低コストでホームページを立ち上げたり、リニューアルしたりしてもらって、そこから一緒に育てていくためです。
すべては、お客様とそのお客様のために……。CMSの開発はまだまだ続きます!
公式サイトでは、インタビュー形式の記事を見ることができます。
DaaSくんの「何のために」へのこだわりやデルター入社前のこぼれ話もありますよ! 果たして、DaaSくんの正体は!?
▼WEB版「DaaSくんに聞いてみた! バージョン4.0の裏話」
http://www.deltar.co.jp/message/2017100417113645.html
わかり わかられ わきまえる ~ communication design ~姿勢と気持ちはつながりあう
今回は、前号で取り上げた電話番の練習をしていたUさんが、いよいよお客様の電話を取ったときのエピソードです。
練習を通じて、朗らかな表情で明るい声を出すことの大切さを学んだUさん。お客様からの電話を初めて取ったときも、元気良く「はい、デルターです!」と声を出すことができました。途中、ちょっと込み入ったことを聞かれてどぎまぎしたものの、担当スタッフへ取り次ぐことができホッと一息。すると、隣にいた先輩のMさんから「背中が縮こまっていて、声量が一定していないよ」と指摘されました。
電話は顔の表情が分からない分、声の良し悪しがお客様の信頼感や安心感につながります。最初はハッキリと話していたUさんでしたが、どぎまぎしたときについ背中を丸めてしまったため、その後はややポソポソとした声になったのに気付いていませんでした。
MさんはUさんに「表情と一緒で、見えないところを大事にすることで声が良くなる。つい弱気になってしまっても、意識して姿勢を正そう。そうすればはっきり話せて、気持ちも落ち着いてくるよ」とアドバイス。
さらに「電話番の基本はお客様の求めに応えることだから。その点、Uさんはちゃんと取り次ぎができたんだし大丈夫! 姿勢、気をつけてみてね」と励ましてくれたのです。
かくして、自分では気付くことのできなかった改善点をMさんに教えてもらえたUさん。今日も姿勢と気持ちを正して、仲間とともに電話番を勤めています。デルターへお電話していただくと、一生懸命なUさんの声が聞けるかもしれませんよ♪
編集後記:えーちゃんの Oh~! Yeahー!
\Oh~! Yeahー!/
\ /~⊂●(((o(*゚▽゚*)o)))
今年は酉年ですが、我が家では今、手塚治虫先生の『火の鳥』が大ブームです。作品を取り上げたテレビ番組を観たのがきっかけで、次の日に早速図書館でまとめて借りてきました。子どもの頃に読んだときも、その壮大なスケールに衝撃を受けましたが、大人になってもいろいろ考えさせられました。
インターネットもパソコンもない時代に、イマジネーション豊かな作品を作り続けた手塚先生を、改めてリスペクトするのでした。
e-LabLetter 第122号 2017/1/18(wed)発行